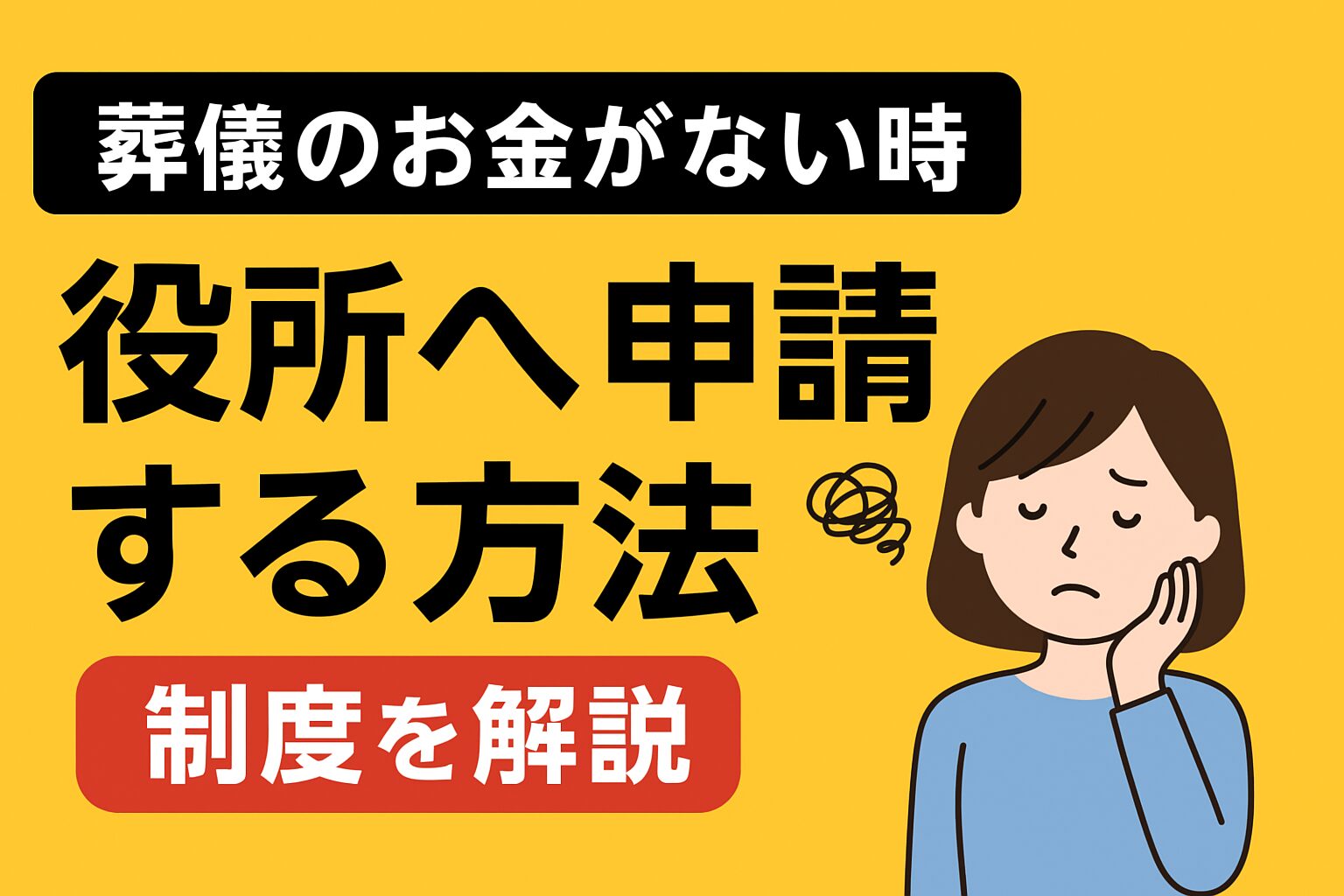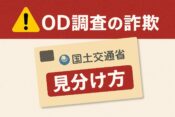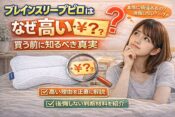葬儀のお金がないとき役所へ申請する方法
「葬儀をしなければならないのにお金がない……どうしたらいいの?」
悲しみの中、費用のことまで頭を抱える方は多いでしょう。
でも諦める必要はありません。公的制度を使えば、自己負担を抑えられる可能性があります。
本記事では初心者にもわかるように、制度のポイントと具体的な手順を丁寧に解説します。
最後まで読んで、「途方に暮れる気持ち」が少しでも安心に変われば嬉しいです。
役所(自治体)の制度を活用すれば、葬儀費用の負担を大きく軽減できる
結論として、葬儀費用をまったく自力で賄えない場合、役所(市区町村)の「葬祭扶助」制度を利用できる可能性があります。
また、故人が国民健康保険などに加入していたなら「葬祭費」や「埋葬料(埋葬費)」といった支給制度を利用して補填を受けられることがあります。
つまり、「お金がない」状況でも、役所への申請をきちんと行えば、自己負担をゼロまたは大幅に抑えて葬儀を進める道が残されているのです。
なぜ制度があるか&どのように機能するか
1. 葬祭扶助制度(生活保護制度との関係)
- 葬祭扶助は、生活保護を受けている方、または生活が困窮している遺族に対して、葬儀に要する「最低限の費用」を自治体が負担する制度です。 出典:小さなお葬式
- ただし「最低限の形式(直葬=通夜や告別式を省く火葬中心)」という条件がつくことが多く、祭壇やお坊さん、返礼品などを含めた一般葬には適用されないことがあります。 出典:小さなお葬式
- 支給上限は自治体により異なりますが、大人で20万6,000円以内、子どもで16万4,800円以内という例もあります。
2. 葬祭費/埋葬料・埋葬費という健康保険・国保の制度
- 故人が国民健康保険(国保)加入者だった場合、「葬祭費」が支給される自治体制度があります。
たとえば横浜市では50,000円が支給される例があります。 出典:横浜市役所 - 故人が健康保険(会社の保険など)加入者だった場合、「埋葬料・埋葬費」が支給されることがあります。
上限5万円がよく見られる例です。 出典:家族葬の市民セレモ - これらは「葬儀をした後に請求する補助金」なので、葬儀後でも申請できる制度です。
ただし申請期限が「葬儀を行った日の翌日から2年以内」など制限があります。出典:小さなお葬式 - 申請できる対象者は基本的に「葬儀を行った(喪主)人」です。
喪主でない場合は委任状が必要な自治体もあります。 出典:いい葬儀
3. なぜ制度を使うと負担が軽くなるのか
- これらの制度は「事前・事後に役所に申請」することで、支給または直接支払の形で補填を受けられるからです。
- 通常、葬儀社とのやり取りで立て替える費用が多くなる中、支援を受けられれば大きな安心になります。
- ただし、制度を使うには「申請書類をそろえる」「役所・福祉事務所で審査を受ける」などの対応が必要です。
実際の申請手順、事例、注意点
具体例:国保の葬祭費を請求する場合
- 故人が国保加入者であったことを確認
- 役所の保険年金課や国保窓口で「葬祭費支給申請書」を入手
- 次のような書類をそろえる:
>故人の健康保険証・資格確認書類 出典:武蔵野市公式サイト
> 葬儀を行ったことを証明する領収書や会葬礼状
> 申請者(喪主など)の本人確認書類、振込先口座情報 - 申請先へ提出(窓口、郵送、電子申請可能な自治体もあり) 出典:一宮市役所
- 審査後、認められれば指定口座に支給されることが多い(1~2か月程度かかる自治体も) 出典:いい葬儀
- ただし、葬儀から2年を超えると請求できなくなる例が多いため、早めの申請が肝心です。
具体例:葬祭扶助の活用ケース
- たとえば、生活保護を受給していた故人、または遺族が生活困窮状態で葬儀費用を支払えない場合には、葬祭扶助制度を申請できます。 出典:小さなお葬式
- 申請先は市区町村の福祉事務所や民生委員窓口、役所の福祉課などです。申請は葬儀を始める前に行う必要がある場合が多いです。 出典:家族葬のこれから
- 審査で、遺族の収入・資産・扶養義務者の有無などをチェックされます。出典:家族葬のこれから
- 承認されれば、葬儀社に対して自治体が直接支払いを行ったり、必要な最低限の葬儀形式を踏まえた葬儀を行うことになります。遺族にとっては「立替なし・自己負担ゼロ」のケースもあります。 出典:小さなお葬式
- ただし、自治体によって支給範囲や条件は異なり、「直葬のみ」「祭壇なし」「宗教儀式の簡略化」などの制限が設けられることが多いです。 出典:小さなお葬式
注意点・最新情報チェックポイント
- 自治体によって支給金額・適用条件・申請手続きが異なるため、住んでいる市区町村のホームページで最新の情報を確認することが欠かせません。
- 葬儀後2年以内という申請期限を過ぎると受給できない場合が多いです。 出典:寄り添うお葬式
- 申請を葬儀前に行う必要がある制度(特に葬祭扶助)は、葬儀業者に依頼する際に早めに相談しておくことが望ましいです。
- 申請者が喪主以外の場合や名義が異なる場合は、委任状や誓約書を求められることがあります。
- 支給対象になる葬儀形式には制限があり、遺族の希望をすべて反映できるわけではありません。
過度な飾り付けや豪華な内容は認められないことが多いです。 - 最新の制度改定や自治体ごとの手続きは、役所や福祉窓口へ直接問い合わせすると安心です。
まとめ
お金がない状態で葬儀を迎えるのは心細く、つらい状況でしょう。
しかし、役所に適切な申請をすることで、葬祭扶助や葬祭費・埋葬料といった制度を活用できる可能性があります。
制度を知らないまま進めてしまうと、本来受けられた補助を見逃してしまうこともあります。
悲しみに暮れる中だからこそ、一歩立ち止まって役所・福祉窓口に相談してみてください。
少しでも支えになれる制度を味方につけて、無理なくお見送りの準備を進めましょう。